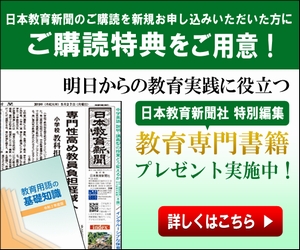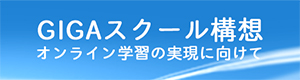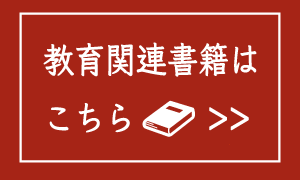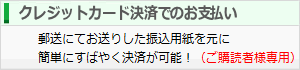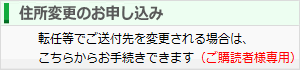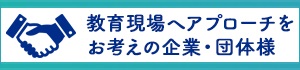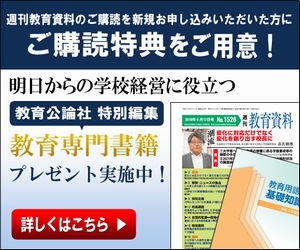国際数学・理科調査 「役立つ」増加も「得意」は減少
国際調査
4日公表の国際数学・理科教育動向調査(TIMSS2023)で「数学や理科を勉強すると日常生活に役立つ」と考える日本の中学生は増加傾向にあることが分かった。算数・数学や理科を「得意だ」と答えた小・中学生は減り、文科省では「実社会・実生活の中から課題を見いだす探究的な学びを促進する必要がある」としている。教科の成績では4年前の前回調査と同様、世界トップ水準だった。
校内カフェ、校内別室…多様な居場所 不登校の高校生 支援充実へ
小・中学校だけでなく、高校でも不登校の生徒の数が近年増えている。全日制や定時制課程での支援の充実に向け、文科省も遠隔授業を受けやすくする制度改正などを通じて、学びの保障を後押ししている。
「校内ハートフル事業」不登校対策で成果発信
大都市中学校長会連絡協議会 横浜大会(上)
大都市中学校長会連絡協議会横浜大会(大会会長=室伏健治・横浜市立上飯田中学校校長、実行委員長=高橋秀吉・同市立本牧中学校校長)が11月14、15の両日、同市のパシフィコ横浜ノースで開催された。政令指定都市など21都市の校長が集い、大都市の中学校教育に関わる諸問題について情報交換、研究協議をする場で、3分科会で六つの発表があった。
子ども、保育者、保護者も「わくわく」 「共主体」の保育を心掛け
めぐみこども園(福井市)の実践から (上)
「芽が出る こども園」を方針として、「ひとりひとりの個性を尊重する保育」「こどもの育ちと学びを支える主体的な遊びを大切にする保育」に取り組んでいる福井市の(社福)めぐみこども園(中戸華恵園長、園児182人)。「共主体」を心掛け、子どももわくわく、保育者もわくわく、保護者もわくわく、地域もわくわくする保育を実践している。2回にわたり、具体的な実践とその実現までに取り組んだ変革の内容を紹介する。
「総合」で独自「プロジェクト」設定 各教科の学び生かす
東京・葛飾区立東金町小
「習得」と「探究」つなぐカリキュラム
課題調べ、下学年へ発表
(公財)パナソニック教育財団の特別研究指定校として、約10年ぶりに都内の公立小学校から選ばれた東京都葛飾区立東金町小学校(河村麻里校長、児童675人)。同校が開発したのは「習得」と「探究」をつなぐカリキュラム。どのような特色があるのか。指導・助言を行う北澤武・東京学芸大学大学院教授のコメントと併せて紹介する。
AIで英会話学習を支援 大阪の中学校と共同開発
早大スタートアップ企業
AIを活用した英会話学習の機会が広まりつつある。文科省は現在、活用強化に向けた実証研究に取り組んでおり、公立中学校での試用も始まった。パートナー企業の一つで、英会話学習サービスを提供するエキュメノポリス(東京・新宿区)はこのほど、早稲田大学主催のシンポジウムで事業の成果を報告。同社は対話型英会話学習サービス、「LANGX Speaking(以下、ラングエックス)」を展開する同大学発のスタートアップで、同大の授業でも活用されている。(本紙特別記者・小出弓弥)
「これからの学校経営」「問題意識」を議論
全日本中学校長会 歴代会長・事務局長座談会
多種・多様な教育課題がある中学校現場。現職を含めた全日本中学校長会会長経験者と同会事務局長を招いた座談会を今年も実施した。今回のテーマは「これからの学校経営」と「私の問題意識」。発言内容の一部を紹介する。(文中敬称略)
教員の多忙感を改善、「開かれた教育課程」推進… 全国普通科高校長会
全国普通科高校長会 総会・研究協議会から(下)
全国普通科高等学校長会の第74回総会・研究協議会が10月31日、11月1日に実施され、全国から約460人の校長・教育関係者らが参集した。前回に続き、発表内容などを紹介する。
その書き込み、大丈夫ですか? SNSでの誹謗中傷、厳に慎んで
多くの人がSNSを活用する時代になった。気軽に重要な情報を発信・受信できる一方で、誹謗中傷が目に付く。プライベートであっても、一人の大人として、子どもたちの前に立つ教員として、SNSの適切な利用が求められている。
自治体36%実施中 昨年度の2倍以上に
休日の部活動 地域移行
B&G財団の関連施設がある自治体の教育長を対象とした調査で、休日の部活動の地域移行について「実施中」と答えた割合は昨年度の2倍以上となる35・7%を占めたことが分かった。同財団は11月22日に、この結果を調査対象となった教育長に報告。この日の会合では、部活動の地域展開に関する事例発表などもあった。