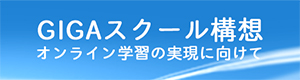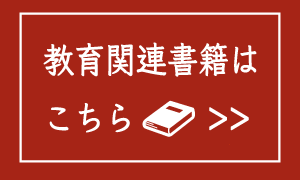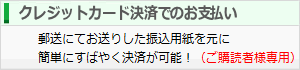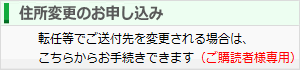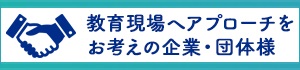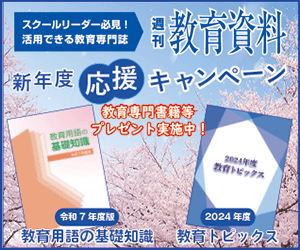夜間中学生徒数 法制定後、最多の1969人
40歳未満が増加傾向
平成28年の教育機会確保法制定後、夜間中学は31校から53校へと増え、生徒数は最多の1969人となったことが文科省の集計で分かった。昨年5月1日時点での集計。この間、60歳以上の生徒は減り、40歳未満が増える傾向にあった。前回の令和4年度調査で生徒数は減っていたが、今回の調査では増加に転じた。2年間で1・3倍に増えていた。
町に根付け「おらほの学校」 秋田・五城目町、住民とつくる「越える学校」
昨年創立150年を迎えた公立小学校が、統廃合と新校舎移転を機に、地域との新たな関係づくりを模索している。「おらほ(私たち)の学校」として住民から愛される存在でありたい。それが学校関係者の思いだ。
東京都新年度予算案 働き方改革に重点
教員業務以外の外部委託推進
東京都は1月31日、新年度予算案を公表した。教育関係では、学校の働き方改革や教員への奨学金返還支援などが柱。不登校児童・生徒への支援など、多様なニーズに対応するための体制も整える。
課題の解決図るために― 傾聴し、浸透させ、要求を
兵庫教育大学 教育行政トップリーダーセミナー (下)
浅野大介・石川県副知事がリーダー論
前回に続き、兵庫教育大学の令和6年度教育行政トップリーダーセミナーの内容を紹介する。今回は関東地区(東京会場)の全体協議に登壇した浅野大介・石川県副知事のリーダー論をまとめる。
「作品展」から「親子の造形遊び」へ
子どものより豊かな生活を目指した行事見直し (上)
「明るく元気に生活する中で、人・もの・ことにかかわり、自分と向き合い伸びていく子ども」「ともに過ごす中で、気持ちよく生活しようとする子ども」「よく見、よく考え、工夫することを通して、明日を創造する子ども」を教育目標に掲げ、「保育を楽しむ保育者を目指して」をテーマに研究を続けている香川県坂出市の香川大学教育学部附属幼稚園(片岡元子園長、園児69人)。「作品展」の見直しなどをきっかけに、子どもの生活がより豊かになることを目指した行事の見直しに取り組んでいる。
アイデア生む「独創力」育成 観点設け授業デザイン
新潟大学附属新潟小学校 (上)
経験踏まえた見方・感じ方 大事に
子どもが自らの経験に根差した見方や感じ方に基づき、新たな価値を見いだす「独創力」の育成に取り組む新潟大学附属新潟小学校(中原広司校長、児童453人)。これまで積み重ねてきた授業実践(各教科等)を踏まえ、児童の変容を手掛かりに育成したい「独創力」の観点(資質・能力)も設定した。本年度、重点に置いたのは「独創力」の発揮を促す授業デザイン。同校の取り組みを上・下で紹介する。
カリマネで学習意欲高める 生徒が「現在地」、今後の方向性把握へ
横浜市立末吉中学校
横浜市立末吉中学校(星野久美子校長、生徒964人)は、カリキュラム・マネジメント(カリマネ)を行うことで、生徒の学習意欲を高める工夫をしている。生徒の抱える課題を踏まえ、学校(学級)目標や学習計画を細かく提示。「学びのプラン」で授業目標を明確化した結果、同校が実施した授業評価で、8割以上の生徒が「授業が分かりやすい」と答えた。
国内初「恐竜学部」を設置 博物館との連携も
福井県立大学
福井県立大学は4月、国内で初めての「恐竜学部」を新設する。「フィールド科学の実践」(地層や岩石、地形の観察)や「デジタル技術を活用した新分野の展開」(大型CT撮影装置などを使用)がカリキュラムの特色だ。新たに開設予定の勝山キャンパスに隣接する県立恐竜博物館との連携も視野に入れる。「恐竜学」を学んだ後、どのような進路が考えられるのか。高校現場でも興味・関心が高い「恐竜学部」の実態に迫る。
英国「支援学級」なく「通級」で 「学習の困難さ」に目
都道府県教委連合会
インクルーシブ教育推進へ 欧州2カ国視察
日本政府が令和4年9月、国連の障害者権利委員会から、「通常学校に特別支援学級があることへの懸念」などを示す勧告を受けたことを踏まえ、全国都道府県教育委員会連合会は昨年9月、インクルーシブ教育推進の参考にしようと欧州2カ国を視察し、先月、その報告書を公開した。特別支援学級を設けていない英国には、「通常級とは別の教室で必要な指導を受ける、通級指導教室のようなイメージ」の仕組みがあることを紹介した。
町を教科書に探究活動 観光、農業など住民ら全面協力
福島県立猪苗代高校
福島県立猪苗代高校(滝田勝彦校長、生徒56人)は、地域社会と連携・協働して学校を運営していく地域協働推進校となり、生徒が地域に学ぶ探究活動を「猪苗代学」として始めて5年目となる。教員は何度も県外の先進校を訪ねて視察するなどして、さらにブラッシュアップされた活動となってきた。
(本紙特別記者・渡邉康一=社会教育士)