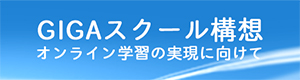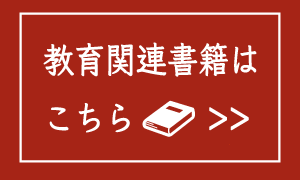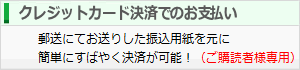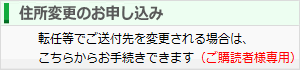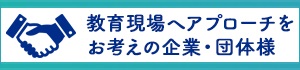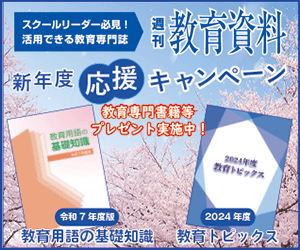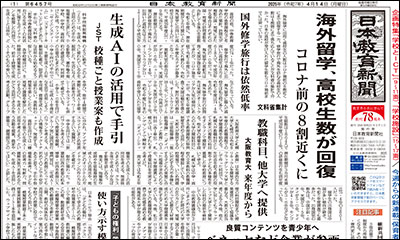
海外留学、高校生数が回復 コロナ前の8割近くに
文科省集計
海外留学に出向く高校生の人数はコロナ禍前の8割近くにまで回復する一方、修学旅行で海外を訪ねる高校生の人数は4割弱にまで落ち込んでいることが文科省の集計で分かった。日本の高校が受け入れた留学生数もコロナ禍前までには戻っていない。
高校無償化を問う 親の所得に関係なく学べる環境を
選ばれる学校へ 魅力化が大事
前原 誠司・日本維新の会共同代表
自民党・公明党の与党と日本維新の会の3党は2月、高校無償化について合意した。公立高校への影響を懸念する声など、教育関係者の中でも賛否が分かれているが、どんな狙いがあるのか。3月下旬、日本維新の会共同代表の前原誠司衆院議員に聞いた。
全日本中学校長会調査研究報告書(下)
前回に続き、全日本中学校長会がまとめた令和6年度調査研究報告書から生徒指導部の結果を紹介する。同部の調査は昨年10月に行い、481校が回答した。報告書は関係者向けの内部資料という位置付けで、一般には公開していない。
「まち保育」の可能性を探る
横浜市立大学と国際校庭園庭連合日本支部がセミナー
横浜市立大学と国際校庭園庭連合日本支部は3月15日、横浜市内で「『まち保育』の視座からこどもとまちの未来を考える―園庭・校庭から企業緑地まで」をテーマとしたシンポジウムを実施した。横浜市立大学のアドバンストエクステンション講座と国際校庭園庭連合日本支部設立5周年記念セミナーを兼ねての開催。「校庭・園庭からまちへ。その実践例から学ぶ」をテーマとした発表の中では「『まち保育』を視座にした幼保小連携」の取り組みが紹介された。
「ちよだ楽」で地域の魅力再発見
東京・千代田区立 全8小学校が成果発表
東京・千代田区立の全8小学校は、児童自らの力で地域の魅力を発見・発信する学習「ちよだ楽」に取り組む。2月27日、同区「かがやきプラザ」を会場に各校の代表児童らが集い、学習の成果を発表した。同区が抱える課題の改善策について提言する姿も目立った。同区教委は子どもが行政に意見を伝えやすい体制の整備に着手している。(本紙特別記者・小出弓弥)
小規模校の教育充実を追究 地域連携で豊かな体験活動
宮崎・五ヶ瀬町立五ヶ瀬中学校
町で唯一の中学校となる宮崎県五ヶ瀬町立五ヶ瀬中学校(菊池憲校長、生徒56人)。町は少人数の学校に最適な教育のために研究を続け、現在は「五ヶ瀬教育グランドビジョン(GV)」の下で、体験活動の充実と、授業力の向上を目指す。同中学校では、根拠となる事実を基に発表することで論理的思考力を育む授業などの実践を重ねている。
小学生対象の起業家教育 生徒がメンターとして参加
栃木県立宇都宮東高校・附属中学校
小学生を対象とした「起業ゼミ」が宇都宮市であり、栃木県立宇都宮東高校・附属中学校(藤田弘光校長)の生徒11人が協力した。令和9年度に中等教育学校への再編が決まった同校は、学校の特色化の一環として起業家教育を取り入れる。3月22日のゼミでは、市内から集まった小学生が身近な「困り事」を解決するアイデアを披露し合った。
小学校教員採用10年目以内 特別支援「経験なし」8割超
校長会が調査
検討会議提言も普及せず
小学校の教員で採用10年目までに、特別支援教育を複数年経験したことがある人の割合は2割に満たないとの調査結果を特別支援学級や通級指導教室を設置する小・中学校の校長会がまとめた。文科省の検討会議は令和4年に「全ての新規採用教師が10年目までに特別支援学級や特別支援学校の経験を複数年経験する」こととしているが、こうした人事措置が期待通りに進んでいなかった。校長会では「国・任命権者の都道府県が採用時に、特別支援学級等の担任の経験を制度として課していくことも検討していくべき」と提案している。
学校運営協議会の活動と並行 住民ボランティアが授業支援
家庭科・体育… 小・中の実技教科中心に
茨城県小美玉市では、学校運営協議会制度と並行し、住民らによる学校支援が活発化している。小・中学校の図工、家庭科、体育といった実技を伴う授業を中心に、ボランティアとして児童・生徒に付き添い、助言したり励ましたりする。教員経験者も参画。ボランティアとして学校に入った大人の側は、活動を通して出会った児童・生徒との人間関係を深めていく。